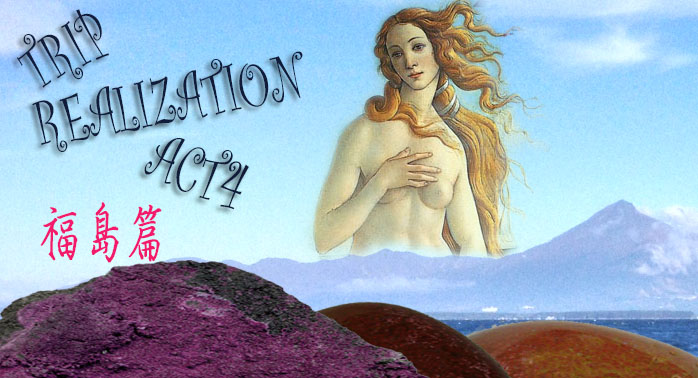
6
南相馬への、二度目の山越えだった。
行く道は国道4号から県道12号を走った。
山中から里まで、何処もかしこも、広域に亘り放射能の汚染土の除染作業が進められ、哀れにも剥き出しになった土、そこに積まれた見るからに悍ましい汚染土を詰めた黒い袋の塊!
そこは間違いなく昔から人が林業、農業、牧畜、そして生活を営んでいた地であり故郷だが、壊滅した。
あの事故から4年目を迎えるが、なんら、いっこうに復興はしていない。
それは不治の病を抱えた体のようだ。
波止場作家のホッファーは語る。
「人間が足を踏み入れると、
どこでも大地が不吉なものになる」
この場合、「人間」は「東電」だった!
その連続が人の歴史だ。
原町は相変わらずゴーストタウンのようだった。
商店通りのほぼすべてのシャッターは閉じている。
もはや商売が成り立たないのだろう。
目の前の横断歩道を中学生か、男の子と女の子が体を寄せあい、若鹿のように足早に横断していく。
一陣の風が吹き抜けていくような印象に、虚をつかれる思いに駆られる。
今回も南相馬行は小松夫妻との三人旅。
夫人は一ヶ月のサンディエゴ旅行から帰国し、「もう少し、早く行ってれば、デイビッドとロスのポールの家に行けたのに、残念」と言うので、ポール? って誰だ? と思い、聞くと、「ポール・マッカトニー」「!」。
つまり、デイビッドは小松夫妻の長女と結婚した息子にあたり、息子夫婦は現在サンディエゴの邸宅に暮らし、デイビッドは映像コンテンツの制作・販売の会社を経営しており、その関係で小松夫人が「ポール」というポール・マッカトニーや「ミック」というミック・ジャガーとも親友らしい。
「孫もポールに会ったの」と、小松夫人は、記念写真を見せてくれた。
なんて、かわいい孫なんだ!

昼には野馬追い通りの旧松本醸造の酒蔵の大屋敷を料理屋にした〈食彩庵〉の座敷にあがり、以前、博物館でお世話になった宍戸さんと人気の重箱弁当を食べながら、雑談。
丹下左膳誕生秘話を聞く。
丹下左膳は、映画で大衆化したが、その原作は林不忘が大阪毎日新聞に連載した『新版大岡政談・鈴川源十郎の巻』である。

執筆のキッカケは浪江町が関係している。
我々が宍戸さんと再会した屋敷の主人は国会議員や日活社長をつとめた松本孫右衛門という。浪江町原町出身。時は、大正末期、場所は上野の料亭。松本は同郷の民謡研究家と相馬藩士の歴史を語りあっていた。その場で筆記役を勤めたのが林不忘だった。そのころは長谷川海太郎と、本名だった。
民謡研究家は米沢の伊達家から付き人として相馬にやって来た左利きの侍のエピソードを語った。
林不忘は新聞連載の依頼をうけ、その下級武士を主人公にした時代小説が閃いたのだった。
取材のため、林は相馬に来て、伊勢屋旅館に10日ほど宿泊、そこで、また民謡研究家に会い、原町生まれの刀術家を紹介され、話しに二本の名刀の伝説を聞き、丹下左膳の人物像をかためていった。
「つまり、あの丹下左膳は、この町から生まれたのです」と、宍戸さんはおっしゃったので、また、好奇心に駆られた。
そして、松本氏が日活社長のとき、トーキー版丹下左膳三部作が伊藤大輔、山中貞雄監督、大河内傳次郎主演で制作された。
自分は実在した坂本龍馬物語よりも架空の丹下左膳が好き。
雛祭りが近づいていた。
小松夫妻から、相馬の雛人形は家々で、独自の人形を持ち、それは美しい、と聞いていた。
別の蔵で、雛祭り展を運良く開催中だった。入館した。

南相馬の旅は前回も意表を突く事象との遭遇が連続したが、その藏内宇宙も衝撃であった!
一瞬、田名網敬一のサイケデリック・ワールドに迷いこんだ錯覚を覚えた。
そこは真の迷宮であり桃源郷であり幻惑的カオスであり、感覚は眩惑へとおちていった。
壁には、エッシャーを遥かに超えるトリック・アートのような、しかし、その技術は人ワザとは思えないパッチワークの作品が埋め尽くし、天井からは吊るし雛か、狂熱放つ極彩色の無数の手縫いオブジェがぶらさがっている。
空間を埋め尽くすイリュージョン、色彩、造形!
呪術力に満ちた祭儀的空間!
しかも、そこは酒蔵内だ。酒精の化身か!
いままで酒蔵を酒場や料理屋や画廊に再利用した店は幾つも見てきたが、何処も伝統に寄りかかりたいしたものではなかった。そのくせ、料金が高いのが相場。
しかし、ここは、なんだ!
甘酒がただで振舞われ、隅に、まるでいつかシルクロードのオアシスのバザールで見た遊牧系婦人たちのような女性たちがいる。
話しに、パッチワークや吊るし雛は、その70代の女性たちの作品と知り、さらに、衝撃を受けた。
と、同時に、〈もろはくや〉の77歳の女将のコラージュ作品を想い浮かべ、おそるべし、福島の女将たち! と感服した。
これは、パッチワーク・モードの先鋭であるアンリアレイジの邦彦に教えてあげようとiPhoneで写真を撮り、彼にメールした。




即、彼から、「やばいっすね。すごい!」「神がかっていますね」「過剰で美しいです」と感想がきて、やはり、この感想はぼくが田名網さんの作品から受ける感慨と同じだった。
流された家にも、放射能被害で放置せざるえなくなった家々にも、この女性が縫った美があったのだろう。
暮らし、暦の中心に「合理」よりも「美」が肝を据えるみたいにあったのだろう。
原町から鹿島へクルマは走る。
日暮れていく地に、寂しげに、新築の一軒家が建ちはじめているが、家を建てるにも建築の人手が不足している。当地の業者が休業、廃業に追い込まれたからだ。
クルマは仮設住宅に到着した。


そこに小松さんの実姉の菅野貞子さんが仮住まいしているのだった。
貞子さんの嫁いだ家は、村上海岸で砂鉄を採取する仕事についていた。
家は、小高にあり、津波の被害はまぬがれたが、放射能被害により帰宅困難地区に指定され、仮設住宅に暮らしている。
仮設住宅には、娘さん家族も別棟に暮らしている。
そこは、あまりに殺風景な施設だった。
原町の町なかにも仮設住宅区はあり、建築物は同じプレハブだが、印象がちがう。
鹿島の施設の周りには、商業施設がひとつもないし、車がなかったら、しかも、お年寄りであったら、さぞ、日々のくらしに困るだろう。
貞子さんの住まいの戸を叩いた。
むかしでいう六軒長屋のひとつのようだった。
戸が開き、貞子さんが迎えてくれる。
あがると、すぐ台所だった。その奥にふた部屋。

そのひとつで貞子さんは日常生活を営んでいる。
コタツに入った。

部屋の随所に、まるで、それが祈りであるかのようにたくさんの布でつくった人形があった。
「お姉さんさんが、自分でつくったんです」
と小松夫人が教えてくれる。
「わたしたちも、家が流され、ここに仮住まいするはずだったんですが、部屋が狭すぎて、とてもお姉さんと暮らしていけない。それで、各地を転々として、猪苗代に流れ着いたんです」
311以降初めて再会したという三人の会話は、シリアスな調子を帯びている。
311は、通常の自然災害の扱いで、それに対する国からの支援金は一律200万円。
しかし、福島では多くの地区が翌日312の原発事故の放射能汚染の被害に遭い、 家はあるのだが、帰宅困難地区に指定され、多くの人が住居に帰れず、他の地やこの地の仮設住宅に移住を余儀なくされた。
その312に対する保証がまったくされてないのが現状だ。
「ここは、4月末までなんだ。そのあと、何処に行けばいんだか。住宅建ててんけんど、あそこは、家、流された人がはいんだろ」と、姉さん。「うちは、帰れんけど、家があるからな」
311は東北全体の自然災害だが、312は福島を襲った人的災害だ。
それに対する支援がなされていず、さんざん叫ばれた「復興」も、いまは虚しくフェイドアウトしつつある。
「サトシが、なんだ、砂鉄なんて言うんで、ついに、サトシも暮らしにこまってさ、変なこと考えて、おら、心配してたんだ。道具なんて揃えた日には、しんしょう傾きゃなきゃいいって。それ、大金、かかるぞ!」
と、会話は本題に入った。あとに、爆笑が弾けた。
「砂鉄の製鉄所やるなんてやったら、どーすんべ思ってさ。資本はかかるしよ。機械なんて買ったら、いくら金あっても足んねえよ。製品つくるまで、商売もたねえよ」
と、貞子さんの心配は冗談ではないので、書記長が事のはじまりから説明した。
ーーある日、猪苗代湖畔に砂鉄の浜を見つけ、その日、帰りに寄った会津の強清水の蕎麦屋の女将との雑談から、砲丸制作を決意した・・・
「猪苗代湖の砂鉄で、砲丸作るんだよ」と、書記長が言う。
「砂鉄は、どこに、あんだ?」
「もう、集めました」とぼくも会話に参加する。
「今日は持ってきてないけど、猪苗代湖にある」と書記長。
「浜に、いっぱい、あんです!」とぼく。
「いっぱいあるの。ふーん。それは黙ってとってもかまわねえの?」
「大量じゃないんです、必要なのは」とぼく。
「だけんど、砂鉄、黙ってとっちゃ、まずいんじゃねえの。権利、買うとか」
相変わらず、貞子さんは心配している。
「お姉さん、とるったって、バケツ、一杯ですよ」とぼくが言う。
黄昏の色のない光が窓から差し込んでいる。窓辺には黄金花月が可憐な白い花弁を咲かせていた。はじめて、この植物の花を見た。貞子さんと花は身を寄せ合って暮らしている。
「バケツ、一杯くらいなら」と、砲丸製造計画には当初から無関心だと察していた小松夫人もフォローしてくれる。
「一杯くらいならな。んだったら、トタンに広げて、そこ、水で流して洗えばいいんだ。チャッポン、チャッポン、流せばいんだろ。したら、砂が流れて、鉄だけになる」
「チャッポン、チャッポン!書記長、それ、コツですよ!」
「しかしよ、サトシは子供んときから物好きだったから、なんか、変なもんがとりついたか、心配だな」
会話はつづく。
森永「砂集めて、水で洗うと、鉄はどのくらい残ります? 半分?」
姉「半分くらいになってんなあ」
夫人「でも、半分とれればいいわよね」
姉「砂の方が、多いだべんな」
森永「そうですか! 水で流したら、全部、砂で流れてしまったら、どうしますか、書記長!」
書記長「アレーって!」
森永「最初、お姉さんに、白装束で巫女のように、水、流してもらいましょう。聖なる水を使って」
書記長「じゃ、姉さんに、洗ってもらうべ。それまで、生きててくれ」
貞子さんは、かつて、南相馬の村上海岸で砂鉄を採取する仕事についていた。
働いていたのは十人ほどの女性だった。採取した砂を桶に入れ、天秤棒で担ぎ、集積所に運ぶ。そこに畳一畳ほどの箱があり、そこで、水を流して、砂と鉄を選別する。
その鉄を箱詰めにし、西金物店の馬車に乗せ、原町駅に運搬す。
そこから蒸気機関車の貨車に積み込み、東京へと送り出す。
「海岸に砂鉄は、いっばい、あったか?」と書記長が聞く。
「うーん、なんぼか。台風んとき、浜のひとところに、大量に、海から砂鉄はあがってきたさ。波、荒いと。静かなときは、来ない」
「北寄貝も、台風のあと、浜に、大量にあがってたでしょ」と夫人。
「砂鉄は、いつも、決まった場所にあがったんだ。嵐んときさ」
「それは、カネになったのかい」と書記長。
「うち、一軒、建っただけさ」
書記長は、貞子さんに聞いた。
「大堀焼きあるだろう? あれに、砂鉄入れて焼いてたって聞いたけど、本当か?」
「わかんねえけど、うちに大堀焼きの花瓶あって、玄関に置いてたんだ、花活けて。したら、自分で蕎麦作って売りにくる蕎麦売りの近藤さんが、それ、見て、こんな色出る花器は初めて見たってびっくりして、おら、それ、大堀焼きの窯元からもらったんだ。そんとき、砂鉄混ぜると、独特の色合いになるって聞いたな」
「それ、いまもある?」
「ある。あの、地震で、ぜんぶ壊れたのに、壊れなかった」
「それは、やっぱり、砂鉄の力だ!」とぼく。
「それ、もらっていいか?」
「興味ねえから、いい」
「行けば、わかるか?」
「わかるべ」
「玄関にあるか?」
「玄関あけっと、あるっべ。青っぽいの。そのままにして、家、でたから、あるべ」
「さっそく、行こう!」
「行きましょう!」夫人も同意した。
姉さんは、砂鉄はサテツではなく、スガネというんだと言った。
小高へと向かった。
原発事故後、全住民13000人が追いやられた町は、家並みがそのままに、しかし無人だ。
貞子さんの家に着いた。

日は暮れていた。車のヘッドライトが家を照らした。
映画でも撮影している錯覚に襲われたが、そこにいるのは、ぼくらだけだった。
車をおり、家に歩いていった。
玄関戸は簡単にあいた。

目に飛び込んできたのは、ヘッドライトの光に浮かびあがった立派な仏壇だった。
玄関の下駄箱の上に幾つかの花瓶があり、書記長が、そのひとつを手にとった。
「重い! 砂鉄が入っている!」
姉さんは家から何も持ち出さなかった。
それを「投げた」と言った。

